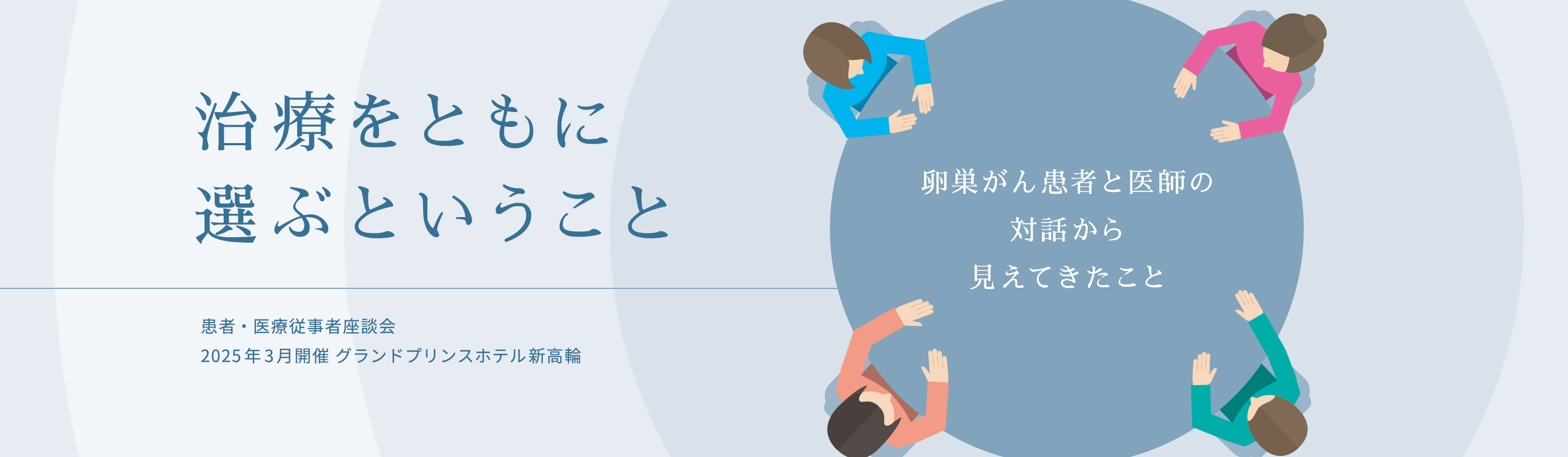
維持療法の選択理由と納得できる治療を受けるための工夫

維持療法を選択した原動力は
“大切な人の存在”
司会:お二人が遺伝子検査を知ったきっかけを教えていただけますか。
にゃんたさん:患者さん向けのSNSを通じて、遺伝子検査や維持療法のことを知りました。自分から先生にその話を切り出したのですが、同じタイミングで先生も提案しようと思っていたようで、検査を受けることができました。
なおさん:母が乳がんだったので、「もしかしたら遺伝かも?」と思い、軽い気持ちで遺伝に関するオンラインセミナーを受けました。その時点では遺伝子検査について全く知らなかったのですが、他の参加者の方々は既に医師から勧められていた方が多いようでした。それがきっかけで自分から先生に検査を受けたいと申し出て、遺伝子検査を受けることになりました。結果は遺伝子変異陽性だったため、維持療法を選択しました。
司会:温泉川先生は、患者さんに遺伝子検査を勧める場合どのタイミングでお話をされますか。
温泉川先生:遺伝子検査には、がん細胞の遺伝子を調べるものと正常細胞の遺伝子を調べるものの2パターンがありますが、将来的な治療選択に特に影響するのは前者です。そのため、がん組織を取った時点、つまり手術後のタイミングで提案することが多いです。
患者さんには、検査結果が治療選択の参考になることや検査の必要性について説明します。その後は患者さんの検査結果に応じて選択肢となり得る治療法を提示していくという流れで、段階的に話を進めていきます。
司会:お二人とも維持療法を選択した理由、維持療法に期待したことを教えていただけますか。
にゃんたさん:維持療法に期待したのは「生きられる期間を延ばすこと」です。実のところ私は結婚してから日が浅く、2019年の乳がんが見つかった後に入籍しました。夫はがんとわかっても結婚すると言ってくれたのですが、翌年には卵巣がんも見つかって、とにかく「夫がいるからまだ死ねない」というのが一番の思いです。「使える薬があるなら全部使ってから考えよう」と思いながら治療を受けていました。
なおさん:私も再発までの期間を延ばすこと、健康に長く生きることを期待して維持療法を受けました。私の場合、当時息子が不登校だったこともあり、「今は死ねない」という気持ちが一番強かったです。おかげさまで現在は息子も大学生になりました。
司会:温泉川先生は維持療法を治療選択肢として提示する際、期待される効果についてはどのようにお話しされますか。
温泉川先生:維持療法の効果については、化学療法とは異なり奏効割合が主要な評価指標とされることはあまりありません。進行卵巣がんの患者さんの場合、再発までの期間を延ばしたり、再発のしやすさを低減したりする治療とお伝えします。

患者さんと医師の
コミュニケーションの工夫
司会:がん治療をしていると、選択を迫られることも多く悩まれる場面もあるのではないでしょうか。納得できる治療を受けるための診察前の心構えや、医師とのコミュニケーションにおける工夫を教えていただけますか。
にゃんたさん:あらかじめ病気や治療について調べて、様々な情報を自らに落とし込んだ状態で診察に臨むようにしています。また、主治医に聞きたいことがあればスマートフォンのメモ機能に全部メモをして、聞き漏れがないようにしています。
人によっては、先生を前にすると何も言えなくなってしまったり怖いと感じる方もいるようですが、私の経験上では診察で少し怖いと思う先生も、手術後の入院時には結構優しく接してくださることが多いです。
診察時は先生も忙しく大変な状況のため、医師への質問があれば、まずは書いておくことをお勧めしたいです。
なおさん:今できる最善の治療を最適なタイミングで受けたい、長生きしたいという気持ちが強かったので、診察前に同じ患者会の方に聞いたり調べたりして、「せっかくの機会だからできるだけ知りたい」という思いで診察に臨みました。
結果的に受けたい治療を受けて現時点で問題なく過ごせているので、セカンドオピニオンも大切な治療選択だったと考えています。
ただ、最初のころは不安で、先生に聞きたいけれどどう聞いたら良いかわからないことも多かったです。そんな時にがん治療を受けた経験のある夫が同席してくれて、代わりにいろいろと先生に質問してくれました。
司会:いろいろな患者さんがいらっしゃると思いますが、先生のお立場としてはどのような思いで診療にあたられていますか。
温泉川先生:医師の性格にもよりますが、私の場合、患者さんに重い診断を告知しなければならないときなどはそれなりに緊張していて、ある程度自分の感情を押し殺しながらお話ししています。
共感してしまうと大切なことが伝えられなくなってしまうので、患者さんからすると少し冷たい言い方になってしまっているかもしれません。
患者さんも不安や恐怖が大きいと思いますし、医師も緊張している場面ではありますが、お互いの感情をぶつける場ではなく建設的なコミュニケーションの場として、思いを共有できるのが理想だと考えます。
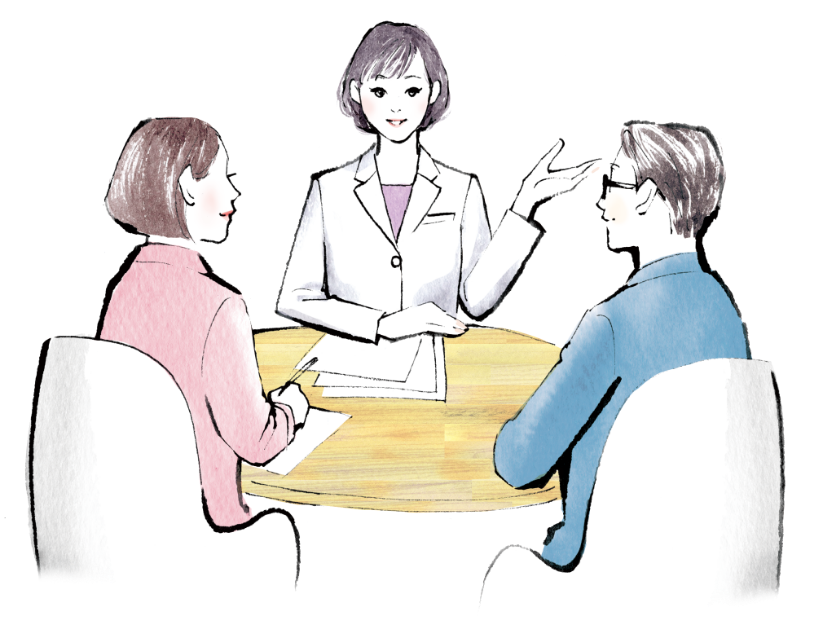
司会:先生が考える、患者さんが医師と上手にコミュニケーションを取るためのコツはありますか。
温泉川先生:最近は以前よりも卵巣がんに関する資料や情報が増え、診療時間内ですべてを説明するのが難しくなっています。医療機関でもらった資料を読んでわからないところがあれば診察時に聞くというように情報を少しでもご理解いただいた上で来院していただくと、お話がスムーズに進み治療を決定しやすくなるかと思います。
-
維持療法
卵巣がんが再発したり、大きくなったりするのを防ぐために、手術や抗がん剤の後に行う治療です。検査でがんが見つからない状態になっているか、がんが残っていても抗がん剤が効いて縮小している場合に行われます。
-
遺伝子検査
遺伝子情報を知るためにおこなう検査のことをいいます。一部のがんでは、がん組織中の遺伝子を調べる検査、親から受け継いでいる遺伝子を調べる検査がおこなわれます。患者さん一人ひとりに適した個別化医療のためには、遺伝子検査の情報が必要となることがあります。
-
再発
手術や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査でがんがなくなったことを確認した後、再びがんが現れることをいいます。
-
化学療法/抗がん剤治療
細胞の分裂機構に作用して細胞の増殖を抑える薬(抗がん剤)を使った治療法のことをいいます。抗がん剤は、作用の仕方によってさまざまな種類があり、単独、または複数の薬を組み合わせて用います。
-
セカンドオピニオン
主治医以外の医師による「第2の見解」のことをいいます。患者さんが治療を選択する上で、悩んだり判断に困ったりしたときなど、さらに多くの情報を必要とする場合に求めることがすすめられています。

